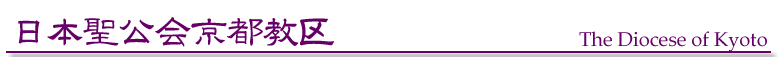 |
||||||
|
2006年4月30日 復活後第3主日 (B年)
|
|
司祭 ミカエル 藤原健久 どうしようもない 聖公会には、年に2回、「断食日」がある。大斎始日と聖金曜日(受苦日)である。断食、と言うからには、全く何も食べないのか、といえばそうではなく、先輩方に聞くところによると、「まともな食事を1食にする」日らしい。これぐらいならできそうな気がして、今年の大斎節は、2日だけでなく、何度か断食してみた。2食抜くぐらい何ともないだろうと思っていたが、意識的に断食してみると、思っていた以上に苦しかった。朝起きた時から空腹感を覚え、その後ずっと、頭の中は「お腹がすいた」で一杯である。1日の内に何度もくじけそうになる。実際に何回かはあきらめて食べてしまった。やっと待望の夕食の時間が来て、一口食べる。さすがにおいしい。けれども、お腹がふくれると、後はいつもの通り、日頃と何も変わらない心持ちになる。断食したからと言って、忍耐強くなるわけでもなく、心が浄められるわけでもなく、信仰的に上昇するわけではない。少なくとも、自覚的には、何の変化もない。
|