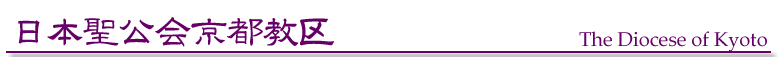司祭 パウロ 北山和民
「道をそれて」
モーセは言った「道をそれて、この不思議な光景を見届けよう。」【出エジプト記3章3節】
この後7節からモーセは「わたしは民の苦しみをつぶさに見、叫びを聞き、その痛みを知る」(出エジプト3:7)、「わたしはある」(同3:14)という神と出会います。
この一連の箇所の重要さは語りつくせません。キリスト教の基盤となる神様、そしてわたし達の想像する神様理解を常に創り変える、実に偉大な箇所です。
この神との出会いのきっかけが、モーセが「道をそれた」と記されていることに今回特に心を留めてみたいと思います。
というのはこの「道をそれた」という表現には「捨てた・断念した」という意味のことばが用いられており、「仕事を怠け、道草好きなモーセ」と言っているようで、不思議な何かユーモアを感じるからです。
「中断される人生」という証(そんな題名の本があったようにも思うが)をもっておられる信徒さんも少なくないと思います。しかしこの箇所は単に個人的な体験の追認に終わるものではなく、歴史民族を超えてあらゆる人を救ってきた「地下水脈」の存在、危機の最中に立ち上がる生きた神の力を汲み取るところだと思います。
ここから二つの知恵を、井戸水のように汲み揚げたいと思います。
ひとつは仕事(モーセにとっての羊飼い)の最中に「どうしてあの柴は燃え尽きないのだろう」と余計な行動をとる子どものような心、ユーモアとも呼べる心が人生を新しく展開するということ。
もうひとつは悩みや疚しさ(モーセにとってエジプトでの不始末)といった辛さ、現代人には時として自殺を考える危機のとき、そんなときにこそ「必ず助けがある」ということ、そしてそれは「がんばっている」ときには気づかない些細な出来事の中に潜んでいるということ。
いずれも助け主と出会うためには自然や生き物に心を向ける「別な感性」いわば「詩人」のような魂が必要なのだと考えさせられます。それは手前味噌といわれるかもしれないが、礼拝の習慣の中に潜んでいるとわたしは考えています。
わたしたちは今日の主日から「聖霊に導かれて、日常現場で証人となる」ことが強調される期節を過ごします。「日曜は礼拝より大事な奉仕をしている」という方もおられるでしょうが、義務や責任に開き直るのではなくまた否定したり後ろめたさ持つのでもない、ちょっと「道をそれて聖書を聞きに行ってみよう」という柔軟な主体性をもって過ごしていただきたいと思います。 以上