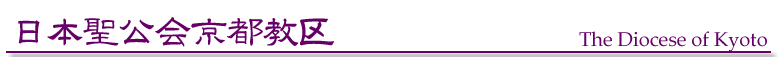司祭 ヨハネ 黒田 裕
驚かれる私たち【マルコ6:1−6】
子どもたちを見ていると、つくづく「驚き」の"天才"だと思います。彼らはどんなに小さなものにも驚くことができます。道端の見過ごしそうな小さな花、はらはらと舞い落ちてくる一枚の葉。たとえそれが大人からすればどんなにつまらないものであっても、子どもたちは「驚く」ことができます。言いかえれば、どんな些細なことにも新鮮な感動をもつことができる、ということです。
しかし、残念なことに、大人になるにつれて、その「驚く力」の前に立ちはだかる「壁」は高くなっていくようです。
イエスさまが故郷で会った人々は確かにイエスさまに驚いています。しかし、彼らの驚きは、先ほど触れた子どもたちのそれとは違いました。つまり、彼らが、驚いたのは、イエスさまの教えそのものにではなく、その教えが、彼の生まれや職業にとても不釣合いに思われたからでした。「この人は、大工ではないか。マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちは、ここで我々と一緒に住んでいるではないか」―。
聖書の他の場面を思い出してみますと、ほうぼうでイエスさまに出会った人々はたいてい彼の不思議なわざや知恵に富んだ言葉そのものに驚いています。そこには新鮮な感動がありました。そうした「驚き」は、ひとが福音にふれたときに惹き起こされる必然的な感情に違いありません。そして実際、「驚く」は、神の良き知らせに直面した人間の状態をあらわす聖書的にも格別な語と言えます。
しかし、先ほどありましたように、イエスさまの故郷・ナザレの人々の「驚き」は、それとは、かなり違うものでした。では、彼らの素直な「驚き」をさえぎっていたのはどんな「壁」だったのでしょうか。それは、あまりの「身近さ」でした。彼らにとって、幼少から知っているイエスさまは、あまりに身近な存在でありすぎたのです。
近すぎると逆に見えないものなのですね。私は、子どもの頃の顕微鏡あそびを思い出しました。6歳くらいでしょうか、顕微鏡を使えるようになった私は、得意になっていろんなものを片っ端から見ていました。そうしているうち、微生物が見えるかもしれないと思い立って、庭の池の水をガラス板に挟んで、ワクワクしながら顕微鏡を覗き込みました。しかし、なかなかピントが合いません。顕微鏡を覗きながら、もう少し、もう少し、とツマミを回しながらレンズを近づけていきました。まだ見えない、もう少し、と思ってツマミを回した瞬間、バキッ! あわてて目を外して見ると、ガラス板は割れ、レンズがめりこんでいたのでした…。
近すぎると、逆にピントがずれてしまいます。近さに頼りすぎると、ピントが合わないばかりか、何かが壊れてしまう、大変なことになってしまうわけです。
ナザレの人々もまた、イエスさまへの近さに頼るばかりに、イエスさまを見誤ってしまいました。血のつながりや土地のつながり―血縁や地縁―というものにだけ頼ってイエスさまを見たためにイエスさまの本来の姿にピントを合わすことができませんでした。
そして、注目したいのは、人々のこうした本来的ではない「驚き」に、こんどは逆にイエスさまが「驚いて」いることです。もし、ナザレの人々に私たち自身の姿を重ねてみるならば、私たちがイエスさまに「驚かれて」しまっているのです。もちろんこの「驚き」は、子どもたちの新鮮な感動としての「驚き」や、聖書的に価値ある人間の反応としての「驚き」とは異なります。
人々は、神さまとの関係において頼るべきものでないものに頼り、ピントがずれてしまいました。「罪」とは、聖書的には「的外れ」なことを意味しますが、ピントがずれるとは、まさに「罪」の状態と言っても過言ではないでしょう。
だとすると、イエスさまに「驚かれる」、「驚かれる」とは、教会でよく使われる「不信仰」や「罪」の別の言い方なのではないかとさえ思えてきます。「罪深い」私たち、というかわりに、神さまに「驚かれる」私たち。
しかし、また同時に、「驚かれる」ことはかえって、私たちには、神さまの業に素直に「驚く」という賜物が与えられていることに気づかされることでもあります。
イエスさまは別の場面で「はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。」と語っておられます。これは、子どもたちが持っている「驚く」力に関係しているように私には思えます。
イエスさまは、私たちが大人になるにつれていつのまにか築いてしまった、「驚く」賜物の前に立ちはだかる高い「壁」を突き破って私たちのところへ来られます。それは、「驚かれる」私から、「驚く」私への招きです。
「驚かれる」私たちから、「驚く」私たちへ。その転換そのものが福音に生かされるということではないでしょうか。