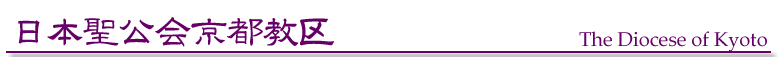司祭 クレメント 大岡 創
「いなくなった息子のたとえ」【ルカ15章11節−32節】
この箇所は「見失われた羊」「なくした銀貨」の譬え話に続く物語です。これらの譬え話で神さまは弱さゆえに道を誤ったものに対して愛と憐れみを注ぎ、その救いと立ち直りを望んでおられることを示そうとしています。
同じ家に住んでいても家族の価値観は一人一人異なったり違っていたりすることは当時も現代も同じようです。この話の中で弟が父から財産の生前贈与を要求しているところに自己中心さと自分の欲望を抑えきれない性格を見出します。これを止めさせるには痛い目に会う失敗体験しかないというのが社会通念かもしれません。結果、父が本人の言い分を適える展開になるのですが、幾多の誘惑の末、すべてを失い、さらに飢えを経験してようやく自分の現実に目覚め、やり直すために父の家に帰る決心をしたのでした。
父は弟のこの目覚めの時を日々忘れることなく待ちわびていたというのです。帰ってくる姿を見つけると自ら走り寄り、抱きかかえて迎え入れる場面は感動的です。
一方、後半に登場する兄は表面上一度も父に反抗せずに働いていますが、内心は自分のことで精一杯になっていたようです。だからこそ父の側で生活していても父の考えや思いやりを受け止められず、ただ父の死ぬのを待っているような虚しさすら感じさせます。「わたしのものは全部お前のものだ」と言われても兄は父に頭を下げることはしなかったのではないでしょうか。また、自分と比べて弟を見下げているところに、一度過ちを犯した者はのちに改心しても認められないと言っているかのようです。当時の律法学者やファリサイ派の考え方と通じるものがあります。神さまは99人の正しい者よりも神さまのふところに入り、神さまと親しく生きようとする一人の罪びとを選ばれました。
この物語から「人はどうしても自分以外のものにはなれない」ことを考えさせられます。出来ることは「自分が本来あった所に戻る」「自分の本来あったものに立ち返る」ということが許されているということ。この弟のように本来父の家にいた者が再びそこに戻ってきたところに物語の出発点があります。
この物語の特徴は放蕩の限りをした息子が「いかに悔い改めたか」ということよりも父の家に戻ってきたときの「父の喜び」の方にあります。「見つけられたときの羊飼いの喜び」「見つかったときの持ち主の喜び」「子が帰ってきたときの父の喜び」にウエイトが置かれています。一度死んだ(いなくなった)がそれを超えるいのちに生かされていく。だからこそ、祝宴を開いて祝うのは当然だというのです。弟に向けて一度も説教をしていないことに父の無条件の喜びが現れているのではないでしょうか。
私たちの信仰生活の歩みは最終的には神さまの喜びであること、その喜びは自分にとってどんな意味があるのかを黙想したいと思います。私たちはともすれば弟のように何度も何度も神さまから離れそうになることがあるかもしれません。そのたびに立ち返り、永遠の神さまに受け入れられていくのです。そのことをことあるごとに思い起こし、神さまに受け入れられていくことの喜びを礼拝の中で味わうことができればと思います。