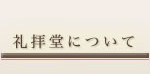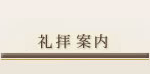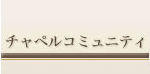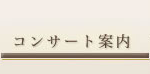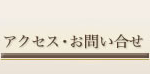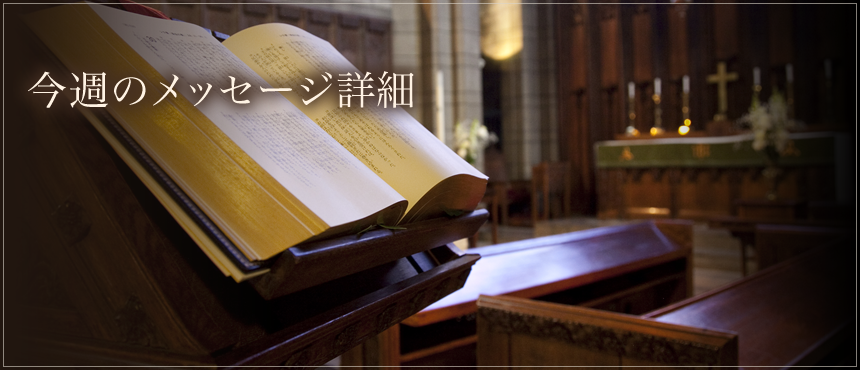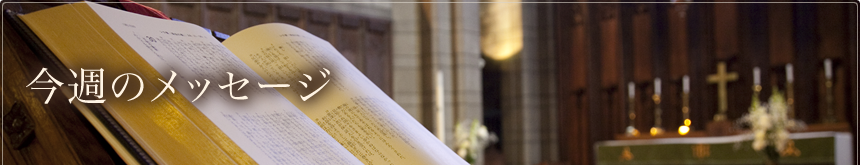「 日常と超越 」
人類が死について認識するようになってから、死後の世界について想像し、死を克服する可能性を模索し始めました。死を通しての思考の跳躍によって人類には超越についての意識が生まれました。そしてそれと共に発達するようになった宗教・神話・シンボル・物語の中で、死は終わりではなく違う形の生の始まりである、という思想が人類を進化へと導きました。つまり人類は死を通して生きることを問い直し、超越のために日常の瞬間に意識をおくようになったのです。生と死とが顔を合わせているように日常と超越も切り離せないのです。心理学者アブラハム・マズロー(Abraham Harold Maslow、1908-1970)が“超越は神秘的な体験ではなく、今この瞬間を忠実に生きる力である”と語ったように、超越は日常の中で体験できます。例えば、帰り道の空、風にそよぐ花、子どもの瞳、素直な会話、暖かな触れ合いなどを通して時空を超えた超越の瞬間を垣間見ることができます。
20世紀を代表する神学者の一人、カール・ラーナー(Karl Rahner、1904-1984)の著書『日常と超越:人間の道とその源』を通してもそれについての理解を得ることができます。彼によりますと、人間は超越的な存在である神様抜きでは存在できず、生きることは全て神様の御手の中にあります。しかし超越的な存在である神様と関わり・交わり・結ばれることは、この世での具体的な命の営みとして日常生活を通してのみ可能なのです。つまり、日常と超越は、まるで体を支える両足のように密接な関係にあるのです。この世での人生が与えられた限り、日常生活の様々な条件に誠実に取り組み、その中で御心を求めつつ生きようとするとき、次第に神様との交わりが生じ神様と結ばれ、この地上で超越を体験するようになるのです。それゆえラーナーの神学では誕生、学び、仕事、遊び、家庭、人間関係、病気、老齢、死など様々な日常の営みが、私たちを超越へと導く大事な場面となります。
ラーナーの神学的な観点を借りて、今日の福音書に登場するマルタとマリアの関係を読み解くことができます。福音書の中、マルタはキリストをもてなすために忙しく働いている姿で、マリアはキリストの足下に座り込んでお話に聞き入っている姿で描かれています。キリストに対する二人の姉妹の姿勢は対照的ですが、奉仕をするマルタは行動的で現実的なタイプとして日常を象徴し、御言葉に集中するマリアは内面的で本質に求めるタイプとして超越を象徴すると言えます。ところが、しばしば教会は二人のことを取り上げてどちらの方が優れているのか、つまり奉仕をするマルタと御言葉に集中するマリアとどちらの方が望ましい姿勢なのか問うことがあります。しかし私はマルタとマリアは、どちらかが優れていてその一つを選ばなくてはならない姿勢であるよりは、むしろ人間の中にある違う側面を象徴していると思います。つまり、マルタとマリアは違う人格であるよりは、神様が誰にも与えてくださった一人の人間にある二つの側面、どちらもなくてはならない側面なのです。日常と超越がかけ離れているのではないように、マルタとマリアは私たちの中の切り離せない要素であり不可欠な側面です。まるで十字架が縦と横の両軸が合わさって完成されることと同じように、私たちの救いのためにマルタとマリアの側面は両方とも必要なのです。
超越は日常においてだけ実現し、日常は超越なしには無意味です。そういった意味で、私たちはマリアを基層とするマルタにならなくてはなりませんし、またマルタの人生を過ごすマリアにならなくてはなりません。このように神様は、私たちがマリアとマルタ、またマルタとマリアとして、つまり日常と超越の側面が互いに支え合いながら生きるようにお作りになり、今もそれを求めておられます。私たちは、カール・ラーナーが語った“人間存在は神様の自己表現そのものである。”という言葉の通りに、自己存在を通して神様の御心を表し、また具現化することができるのです。
<福音書> ルカによる福音書 10章38~42節
38一行が歩いて行くうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女が、イエスを家に迎え入れた。 39彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足もとに座って、その話に聞き入っていた。 40マルタは、いろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。「主よ、わたしの姉妹はわたしだけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。」 41主はお答えになった。「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。 42しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。」