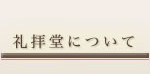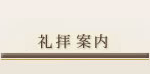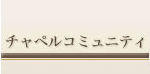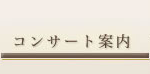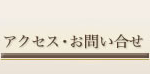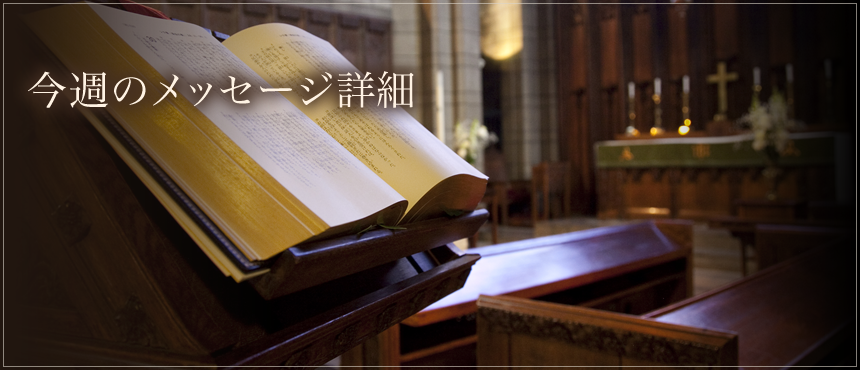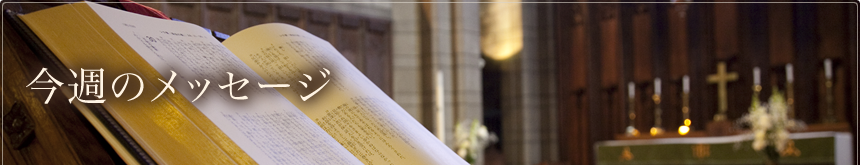「 にじり口 」
戦国時代から安土桃山時代にかけての茶人として茶聖とも称せられる千の利休(1522‐1591)が茶道を確立したときにキリシタンによるキリスト教の影響を多く受けたという話は有名です。例えば、濃茶点前の場合には参加者が茶碗の廻し飲みをしますが、それは聖餐式の陪餐のやり方を真似たものだと言われます。また、茶室にはにじり口という小さな入り口がありますが、それもキリスト教の影響の一つです。にじり口は高さが2尺3寸で幅が2尺2寸程度、つまりおよそ70×65cmの本当に小さくて狭い戸口ですが、そこから客人を迎えるようになっています。いくら背の低い人だとしても体を屈める格好で、敷居にひざまずき両手をつけないと入ることができないのでにじり口と言うようになったそうです。この発想は、今日の聖書の「狭い戸口から入るように努めなさい。」(24節)というみ言葉に由来していると言われていますが、逆に今日の私たちはそのにじり口に見立てて聖書が教えている狭い戸口についての理解を得ることができます。
どのような身分の人であっても頭を下げない傲慢な態度で、または刀を腰に差したままの状態では茶室に入ることはできないことをにじり口が示しています。それと同じように今日の福音書が伝えている狭い戸口とは、体を屈めて低くしたり身に着けている余計なものを捨てたりしないと入ることのできないものです。そのように、狭い戸口から入るためには低くへりくだるものにならなくてはなりません。そしてもう一つ、戸口が狭いと多くのもの体に抱えて入ることはできませんので、入るのに邪魔になるものは捨てなくてはなりません。つまり、偉そうに肩をそびやかしたままの姿勢、または両手で何かを沢山持ったままの姿勢では、狭い戸口から入ることはできないのです。
では、キリストが「入るように努めなさい」と語られた狭い戸口とは何を象徴するものなのでしょうか。狭い戸口に入るとその向こうには何があるのでしょうか。ユダヤ人の「主よ、救われる人は少ないのでしょうか。」(23節)という質問からも分かりますように、狭い戸口の向こうには救いが待っています。わざわざ体を屈めたり、ひざまずいたり、両手に握りしめているものを手放しながらも、入ることができるように努める狭い戸口こそ、私たちを救いへと導く戸口、まさに真理そのものを象徴すると言えます。そして救いと真理として狭い戸口は、「後の人で先になる者があり、先の人で後になる者もある」(30節)不思議な戸口でもあるので、入ることができるように努めることが求められるわけです。
ユダヤ教のラビが弟子たちと旅に出ました。ある日、弟子の一人がラビに聞きました。“先生は以前、真理というのは道端の小石のようなものだと、だからどこにでもあるのだとおっしゃいました。それではなぜ人々は、そのように近くにある真理を悟ることはできないのでしょうか。”すると先生は“確かに真理は道端の小石のようにどこにでもある。けれども、それは腰を屈めなければ拾い上げることができないものでもある。殆どの人々は腰を屈んで自分のことを低くすることをしないから悟れないのだ。”と答えました。
では皆さんが今、救いと真理の狭い戸口の前に立っているとしますと、そこへ入れる状態なのでしょうか。もしかすると、狭い戸口に入ることを邪魔する何かを持っているのではないでしょうか。それぞれ違うと思いますが、人は誰であれ手放したくないから両手で強く握っているため、または大事だから頭に乗せているため、狭い戸口から入ることを邪魔している何かを多かれ少なかれ持っています。それは金、物、人などの物質的なものから、肩書や名誉、性格や習慣、過去の記憶や固定観念、価値観や理念のような精神的なものまで色々あると思います。ではいかがでしょうか、皆さんにとっては何が狭い戸口から入ることを邪魔しているのでしょうか。
<福音書> ルカによる福音書 13章22~30節
22イエスは町や村を巡って教えながら、エルサレムへ向かって進んでおられた。 23すると、「主よ、救われる者は少ないのでしょうか」と言う人がいた。イエスは一同に言われた。 24「狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。 25家の主人が立ち上がって、戸を閉めてしまってからでは、あなたがたが外に立って戸をたたき、『御主人様、開けてください』と言っても、『お前たちがどこの者か知らない』という答えが返ってくるだけである。 26そのとき、あなたがたは、『御一緒に食べたり飲んだりしましたし、また、わたしたちの広場でお教えを受けたのです』と言いだすだろう。 27しかし主人は、『お前たちがどこの者か知らない。不義を行う者ども、皆わたしから立ち去れ』と言うだろう。 28あなたがたは、アブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。 29そして人々は、東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。 30そこでは、後の人で先になる者があり、先の人で後になる者もある。」