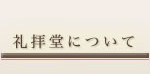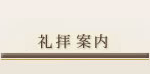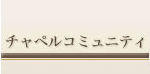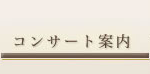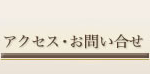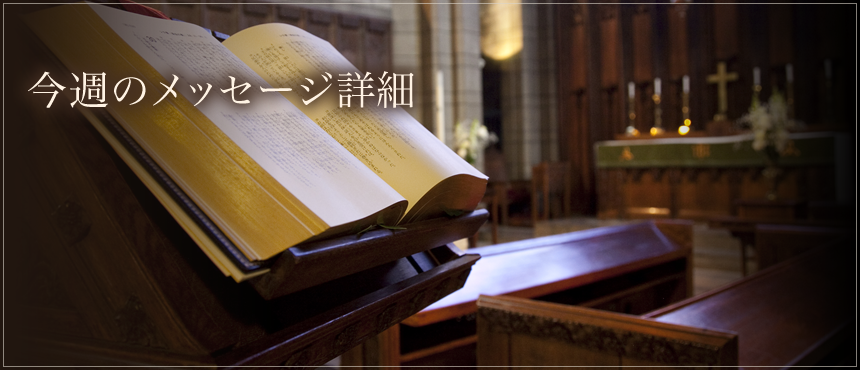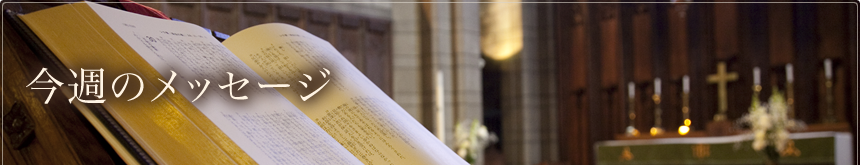「 吾唯知足 」
昔々、高価な服を着て毎日派手に遊び贅沢な暮らしを楽しんでいた金持ちと、その金持ちの家の前に横たわって食卓から落ちる物で少しでも腹を満たそうとしていた物乞いがいました。聖書には、物乞いにはラザロという名前がありましたが、金持ちには名前がありませんでした。存在のアイデンティティを表している名前のある無しからも分かりますように、天から二人の様子を見ていた神様は物乞いの方に目をとめました。ある日、二人ともに死にましたが、貧しい物乞いのラザロは天国へ行き、金持ちは地獄に落ちました。なぜ死後の二人の立場が逆転したのか、その理由について多くの人は疑問に思いますが、単純に金持ちだから地獄に落ち、貧しい人だから天国に行ったとは考えられません。ではなぜでしょうか。
取り分け、金持ちが地獄に落ちたのは、金持ちだからでも派手な生活を楽しんでいたからでもないのです。然るべき理由を探るとしますと、それは家の前で横たわっていた貧しい物乞いにご飯一杯でも与える憐れみの心がなかったからだと推察することができます。つまり、犬が来て体の出来物をなめるほど厳しい状況に置かれていた貧しい人に、自分たちの食卓から落ちるわずかな食べ物くらいしか与えなかった、その心の貧しさが大きな理由だったのです。もしかしたら金持ちは、沢山の金を持っていたにも拘らず、それに満足することなくもっと多くの金を貯めておこうとしていたので、そのような過ちに陥ってしまったかもしれません。満足することも感謝することも知らなかった金持ちこそ、本当の意味で貧しい人だったのです。
京都の世界遺産である龍安寺に「知足のつくばい」があります。つくばい(蹲踞、蹲)とは、茶室に入る前に手を清めるために置かれた背の低い手水鉢のことを指します。その「知足のつくばい」には、珍しく文字が彫られています。中央には四角の水を溜める穴があり、それを漢字の「口」に見立て、それの上下左右に4文字(口の上に「五」右に「隹」下に「疋」左に「矢」)が刻まれていますが、それを上から時計回りに「口」を付けて読んでみると「吾唯足知(われ唯だ足るを知る)」となります。つまり、私に必要なことは足るを知るだけであるという意味の言葉が彫ってあるのです。足るを知るとは、満足することを知る人は、少しも不平不満の心を起こさないため心に落ち着きがあり人生そのものが平安に包まれることを表します。
これは仏教の経典『遺教経』に由来しますが、それには次のような言葉があります。「足るを知る人は地面に寝るような暮らしでも安楽だ。足るを知らないものは豪邸にいてまだ満足がいかない。足るを知らないものは豊かであっても貧しい。足るを知る人は貧しくても豊かである。」お釈迦さまだけでなく、古代中国の思想家の老子や荘子も「足るを知る者は富む」という教えを残しました。また現代においても、報酬の大半を寄付し自分は月に約10万円で生活したため、世界で最も貧しい大統領だと言われたウルグァイの元大統領ホセ・ムヒカ(José Mujica、1935‐2025)は「貧しい人とは少ししかものを持っていない人ではなく、無限の欲のためいくらあっても満足しない人のことだ」と語りました。
では皆さんは貧しさと豊かさについてどのような思いを持っていて、その基準は何だと思いますか。確かに世界には飢餓に苦しむなど経済的に貧しい人々が沢山いて、それは解決しなくてはならない重大な問題です。しかし、その一方で沢山持っているにも拘らず満足することを知らない心の貧しい人々もいるのです。この二つの問題は別々の事柄であるというよりは、表裏一体のものだと言えます。金などの物質と心や精神のことは分離されているものではないからです。つまり、経済の問題は心の問題であり、宗教や信仰の課題でもあるわけです。では、両者の問題を解決するためには何をどのようにすれば良いのでしょうか。そのために私たちができることには何があるのでしょうか。
<福音書> ルカによる福音書 16章19~31節
19「ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日ぜいたくに遊び暮らしていた。 20この金持ちの門前に、ラザロというできものだらけの貧しい人が横たわり、 21その食卓から落ちる物で腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやって来ては、そのできものをなめた。 22やがて、この貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。 23そして、金持ちは陰府でさいなまれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが、はるかかなたに見えた。 24そこで、大声で言った。『父アブラハムよ、わたしを憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、わたしの舌を冷やさせてください。わたしはこの炎の中でもだえ苦しんでいます。』 25しかし、アブラハムは言った。『子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今は、ここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。 26そればかりか、わたしたちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこからわたしたちの方に越えて来ることもできない。』 27金持ちは言った。『父よ、ではお願いです。わたしの父親の家にラザロを遣わしてください。 28わたしには兄弟が五人います。あの者たちまで、こんな苦しい場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。』 29しかし、アブラハムは言った。『お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。』 30金持ちは言った。『いいえ、父アブラハムよ、もし、死んだ者の中からだれかが兄弟のところに行ってやれば、悔い改めるでしょう。』 31アブラハムは言った。『もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。』」