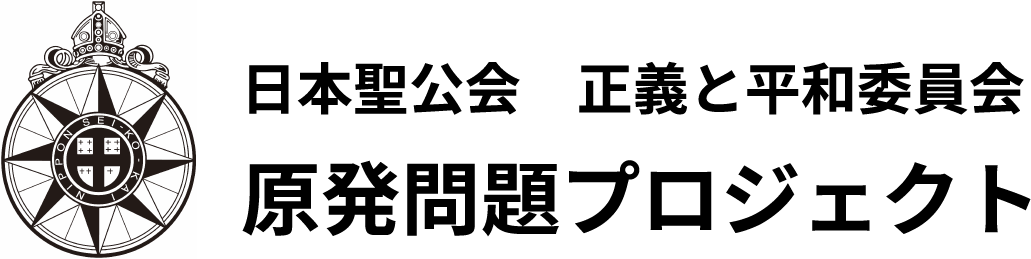東京電力福島第一原子力発電所事故、その後…廃炉への課題と展望 “Q&A”
深刻な事故である「レベル7」の最悪の事故評価を受けた、東京電力福島第一原子力発電所は、運転中だった1〜3号機で電源喪失により炉心冷却ができなくなり、核燃料が溶け落ちるメルトダウンにいたりました。4号機は運転停止中だったためメルトダウンにはいたりませんでしたが、1号機、3号機に続き水素爆発を起こしました。その後、福島第一原発では1〜6号機全ての廃炉が決まり、廃炉作業が行われています。
政府は2051年までに廃炉を完了するとしていますが、事故から13年半超を経た今も収束の見通しは立っておらず、その実行性は疑問視されています。
いまだ決定的な打開策がないと言われる中、廃炉に関する簡単なQ&Aを作りました。
廃炉への課題と展望 “Q&A” 2024年9月12日記
-
「廃炉」にするための最難関は?
-
1号機~3号機にある推定880トンの核燃料デブリの取り出し。
- 核燃料デブリ:
核燃料が溶けて圧力容器の底を突き抜け落下し、炉心構造物やコンクリートなどと混ざって原子炉格納容器に固まっている。核燃料デブリは非常に硬く、また原子炉格納容器は人が入ると死んでしまうほど放射線量が高いため、削ったり砕いたりして遠隔ロボットで回収するしかない。 - ロボットアーム:
核燃料デブリにアクセスするための遠隔ロボット。全長約22m、重さ約4.6t。 国の補助事業の一環として、国際廃炉研究開発機構や三菱重工業、英国企業が2017年から共同開発。 開発費を含めた原子炉の内部調査事業には約78億円の国費が投じられている。 - 東京電力は2号機の核燃料デブリの試験的取り出しを2024年8月22日に開始予定であったが人為的ミスで準備作業を中断。その後作業工程の確認を終え9月10日に再開したが、採取装置の先端についたカメラの映像が遠隔操作室に送れなくなり9月17日再度中断、再開は未定。2021年の開始計画から3年遅れ。これまで3回延期をしたが、今回の2回を加えると5回目の延期。
- 核燃料デブリ:
-
政府の計画は?
-
2024年3月に政府の専門機関である原子力損害賠償・廃炉等支援機構が新工法3案を提案。
- 冠水工法:核燃料デブリを水につけた状態にして取り出す。
- 気中工法:核燃料デブリを気中で取り出す。
- 充填固化工法:充填剤を注入して核燃料デブリを安定固定化してから掘削などして取り出す(気中工法との併用)。
- 東京電力は、2025年度の上期を目途に本格的な取り出しの工法を具体化する方針を決めました。主に気中で作業をする「気中工法」を軸に、「充填固化工法」の実現性の検討を進めるとしています。廃炉は特殊な条件や環境で行う未経験の作業です。現時点では廃炉への確固たる道筋が見えていないのが現状と言えます。
-
いつまでに完了?
-
政府は2051年までに完了する、としているが…
核燃料デブリの総量は推定880トン。1日あたり100キログラム回収出来るとしても、年間の稼働率日を200日として40~50年かかる。- ロボットアームで一度に取り出せるのは、試験的とは言え耳かき1杯、3g以下。
専門家の多くが、この方法で2051年までに全量を取り出すのは不可能との見解を示している。
- ロボットアームで一度に取り出せるのは、試験的とは言え耳かき1杯、3g以下。
-
核燃料デブリの試験的取り出し後の計画は?
-
東電は2号機での取り出し量を徐々に増やし、3号機では2030年代初めに開始、その後1号機でも開始する方針を示している。
- 3号機では建屋全体を水没させるなどの計画もあるが、現在は構想段階。
-
核燃料デブリ取り出し後の問題は?
-
日本原子力学会の廃炉検討委員会によると、汚染した機器、構造物、汚染土壌などを撤去して敷地が再利用出来るようになるのには100年以上かかるとしている。その上、撤去後の処分先の見通しは立っていない。
-
他にはどのような問題が?
-
- 地下水などが原子炉建屋に流入することで汚染水が増え続けていること。このままでは、いつまでも汚染水を海洋放出し続けることになる。
- 汚染水処理で発生する放射能汚泥も大きな問題。処理の問題だけでなく、容器から漏れ出すリスクもある。
-
核燃料デブリ取り出し計画、行き詰まり。では、どうすべきか?
-
核燃料の専門家で日本科学者会議・原子力問題研究委員の岩井孝さんは、自身の講演やしんぶん赤旗のインタビューに答え、以下を提案している。
【1】「核燃料デブリを全量取り出して更地にする」という方式にこだわらないこと。
- 廃炉に伴って発生する膨大な放射性廃棄物をどのように処理・処分するのかは全く不透明で大きな課題。
【2】まずは一定程度安定な状態を早く実現し、見守り続けながら時間をかけて国民的議論を重ねる。
-
当面、具体的にどうする?
-
核燃料の専門家で日本科学者会議・原子力問題研究委員の岩井孝さんは、自身の講演やしんぶん赤旗のインタビューに答え、以下を提案している。
【1】核燃料デブリの取り出しや原子炉解体をせず、原子炉本体などは堅固な構造物で覆い、さらに盛り土をする。
【2】下部にお椀状の「地下ダム」を設置し、地下水と遮断する。
- メリット:
①放射能の拡散量を抑える。
②廃止措置の工期の短縮。
③作業員の被ばくの減少。
④処分地の負担軽減。
【3】少なくとも数十年間、その状態で安全を確保し続ける。その間に、
- 核燃料デブリを全て取り出すのか、
- 原子炉を解体するのか、
- 大量の廃棄物をどこに処分するのか、などの社会的合意をつくる。
- メリット:
-
原子力市民委員会の提言は?
-
原子力市民委員会(座長=大島堅一龍谷大学教授)が2024年3月に提言を発表。
- 汚染水発生量ゼロの目標を明確化する。
- 核燃料デブリ取り出しを中止して安全に長期遮蔽管理する。
- ALPS(多核種除去設備)処理汚染水の海洋投棄が続くことはこれ以上看過できない状況にある。
- 政府が定めた工程表には、汚染水発生量ゼロの目標がないうえに、核燃料デブリの全量取り出しの技術的見通しが立っていない。
-
他の原発の廃炉も含め、どうすべきか?
-
- 政府も東電も現実から目を逸らさず、これまでの原子力政策を続けてきた責任と誤りを率直に認め、方向転換をする。
- 政府も東電も、現在の技術での廃炉は不可能と認め、これまでの廃炉に向けた「中長期ロードマップ」を全面的に見直す。
- 現に発生したものは、何らかの形で安全に保管せざるを得ない。原子力政策に賛成の人も反対の人も、廃炉の最終的な形をどうするのかについて正面から真剣に考え、そこに向けた具体的な技術開発を進める。
(文責:原発問題プロジェクト委員・池住圭)